先日、甲府方面へ行った時のこと。夜空を焦がす「大」の文字が!

なんて思いながら、ふと石和方面に目をやると…ん?あっちの山にも何やら光が。目を凝らしてみると、それはまるで神社のマーク「⛩️」のような、独特のシルエット。

「あれって…もしかして、石和の『あれ』じゃん!」
そう、笛吹市の春の風物詩、「笈形焼き」のライトアップ。甲府の「大」と石和の「笈」マーク、まさかの同時点灯!山梨県民でも、この時期に両方見られるって、ちょっと珍しいんじゃないでしょうか?
…で、ここで気になるのが、石和の山に浮かぶ、神社のマークみたいな「笈」って一体何?ってことですよね。
山梨の夜を彩る二つの光。「大」は知ってるけど、「笈」って?
甲府の山に浮かぶ大きな「大」の文字、これはもう説明不要ですよね。山梨県民なら誰もが知る、大文字焼きのシンボルマーク。
でも、石和の山に光る「笈(おい)」マークは、もしかしたら「何それ?」ってほとんどの方が思っているのではないでしょうか。
「笈(おい)」というのは、簡単に言うと、昔の修験者(山伏)が山の中で修行する際に背負っていた、箱型の道具のことなんです。経典や食料、着替えなど、山中での生活に必要なものを入れて持ち歩いていました。形は、ちょっと大きめの木箱みたいなイメージですね。
で、この「笈」の形を、笛吹市ではLEDのライトアップで山に浮かび上がらせるんです。これが「笈形焼き」。御坂山地の笈形山という山で行われる、春の風物詩なんです。
なぜ「笈」の形を光らせるのか?それは、この地がかつて修験道の霊場として栄えた歴史があるから、とか、武田信玄が修験者を重用したから、とか、色々な説があるみたいです。いずれにしても、地域の歴史や文化が詰まった、神秘的な光のモニュメントと言えるでしょう。
遠くから見ると、その独特の箱型のシルエットが、神社のマーク「⛩️」にちょっと似て見えるんですよね。だから、「神社のマークみたい」と感じた人もいるかもしれません。
いつもの風景に宿る、地域の物語
普段何気なく見ている山々の光も、こうして一つ一つ紐解いてみると、その土地の歴史や文化が深く関わっていることが分かります。
夜空を焦がす「大」の文字は、先祖を敬う心の表れ。そして、山に浮かぶ「笈」の光は、山岳信仰や修験道の歴史を今に伝える象徴。
別々の場所で、別々の意味を持つ二つの光が、同じ夜空に共演しているのを見ると、なんだか不思議な感動を覚えます。山梨の夜って、意外と奥深い物語を秘めているんですね。



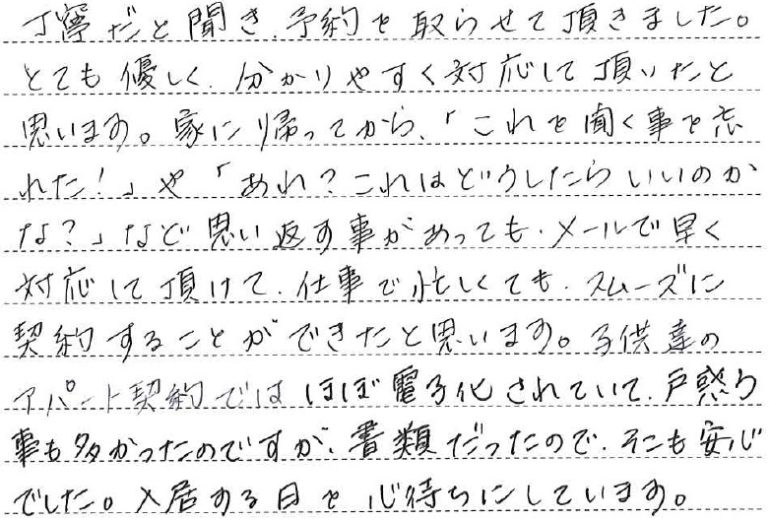





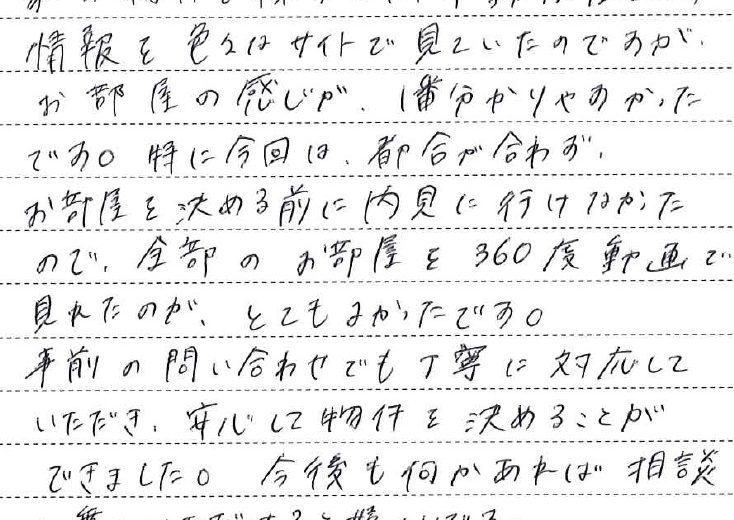


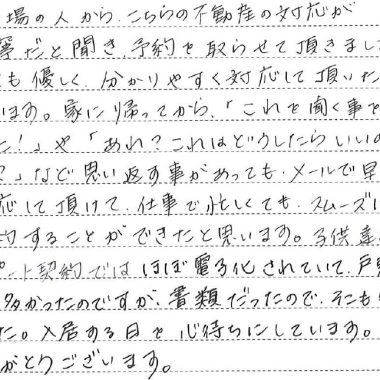


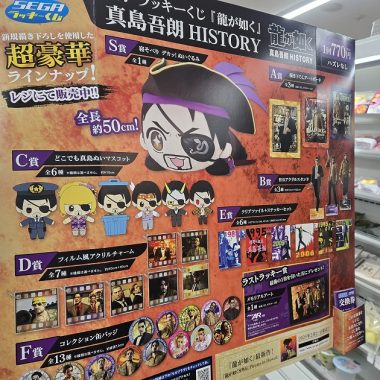









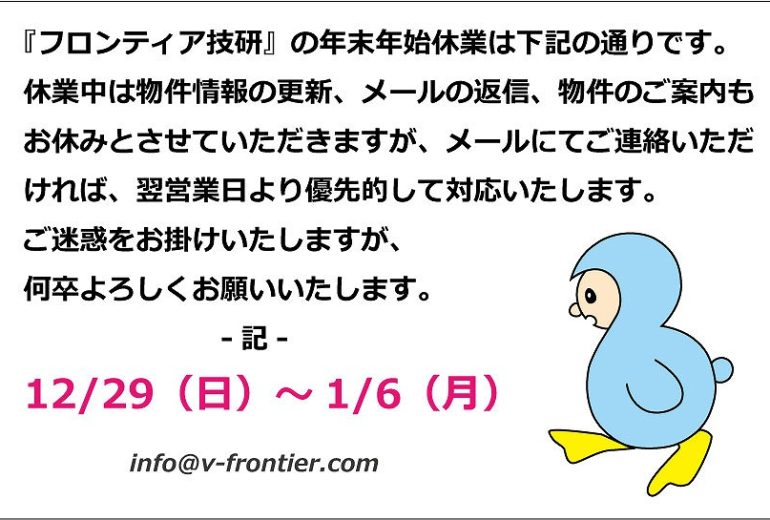




コメント